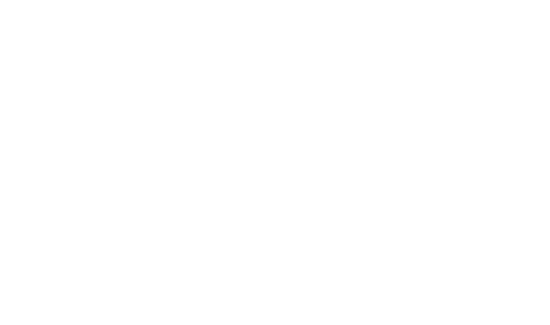【2025年10月施行】育児・介護休業法の改正ポイント
2025年10月1日より、育児・介護休業法が改正されました。
本改正に伴い、就業規則の見直し等が必要となるため、対応を進めておきましょう。
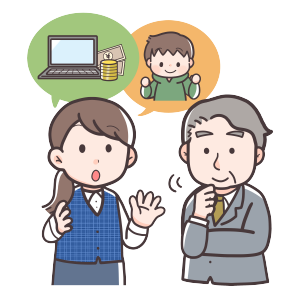
改正内容の概要
1.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
《選択して講ずべき措置》
① 始業時刻等の変更
次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
※ 「フレックスタイム制」と「始業終業時刻の変更」のどちらも選べる制度を設けたとしても、措置を2つ設けたことにはなりません。
※ 「始業終業時刻の変更」については、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。
② テレワーク等(10日以上/月)
一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
※ 原則として、時間単位で取得可能とする必要があります。
※ 3か月で30日など、平均して月10日以上利用できる仕組みとしても問題ありません。
③ 保育施設の設置運営等
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
※ 保育施設を設置する場合については、原則として事業所ごとに設置する必要がありますが、保育施設を設置した事業所(A事業所)の近くの事業所(B事業所)の対象労働者が当該保育施設を利用できる場合は、B事業所も措置したこととして差し支えありません。
※ 保育施設は必ずしも事業所内にある必要はなく、通勤途上など合理的に利用できる範囲に設置されていれば措置を講じたものとみなされます。
※ 事業主が福利厚生サービス会社と法人契約をして会費を支払うことにより、労働者が当該会社が提携するベビーシッターのサービス等を選択・利用できるようにしている場合についても措置を講じたことになります。
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
※ 原則として、時間単位で取得可能とする必要があります。
※ 休暇を取得している期間については、無給でも問題ありません。(会社独自に法を上回る措置として有給としても可)
※ 付与日数を半年につき5日、1か月につき1日等とし、合計して1年に10日以上付与する仕組みとしても問題ありません。
※ 就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられます。(子を迎えにいく、子が就学する小学校等の下見にいくなど)
⑤ 短時間勤務制度
一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
※ 1日の所定労働時間が6時間以下の短時間労働者についても、柔軟な働き方を実現するための措置の対象となります。
※ 短時間労働者も含めて、「短時間勤務制度」と「それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置」の2つ以上を講じた場合は、措置義務を履行したものとされます。
⚠ 注意
労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を果たしたことにはなりません。
企業単位で措置を考えるだけでなく、事業所単位、事業所内のライン単位や職種ごとに講ずる措置の組合せを変えることとしても差し支えないとされています。
会社は、選択した措置に応じて就業規則の変更が必要となるほか、制度の対象から入社後1年未満の者や所定労働日数が週2日以下の者を除外する場合には、労使協定を作成し、労働者代表と締結する必要があります。
弊社では運送業・タクシー業などで本改正に伴う就業規則改定の支援を行っていますが、① 始業時刻等の変更、④ 養育両立支援休暇、⑤ 短時間勤務制度のいずれかを選ばれる会社が多い印象です。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
・3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
| 周知事項 | ① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
| 個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※ ①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。 |
⚠ 注意
個別周知と意向確認は、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出が円滑に行われるようにすることが目的であり、取得や利用を控えさせるようなことは行ってはなりません。
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
・事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
| 意向聴取の時期 | ① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
| 聴取内容 | ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
| 意向聴取の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※ ①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。 |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
・事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
《具体的な配慮の例》
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整・労働条件の見直し 等
「個別の周知・意向確認」は、育児休業制度等の周知と利用の意向確認に留まっていたのに対し、「個別の意向聴取・配慮」は、仕事と育児の両立を円滑にすることを目的として、その両立を妨げる要因の改善につながるよう就業条件等について聴取し、その意向に配慮することが求められます。
「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」と「子が3歳になる前の個別の意向聴取」については、いずれも労働者の子が3歳になるまでの一定の期間に実施しなければならないため、事業主には労働者の子の年齢を正確に把握しておくことが求められます。
特に、労働者が扶養していない子については会社側が情報を把握しにくいケースもあるため、今後は労働者の子の情報を把握・管理できる体制の整備がより重要になってくるでしょう。
育児・介護休業法の改正については、厚生労働省から就業規則の規定例やパンフレット、各種様式が公表されていますので、詳細はそちらをご確認ください。
弊社へのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム
☎ 03-6721-1090(平日9:00~18:00)